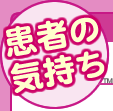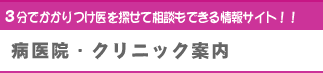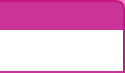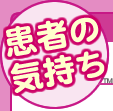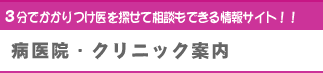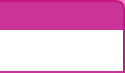子宮頚部にできる悪性腫瘍を総称して呼ぶことが多いです。婦人科悪性腫瘍の中でも最も頻度が高い病気です。
頻度
子宮頚癌は、女性生殖器の悪性腫瘍の中で最も頻度が高く、約50%に達する病気です。しかし、最近では、患者数、死亡数とも減少傾向にあり、女性の癌による死亡の原因では、1970年の第2位から1990年には第8位となっています。また、癌検診の普及によって、1993年の統計では、臨床進行期O期、およびI期の早期癌の割合が子宮頚癌全体の65%以上を占めるまでになっています。
好発年齢
子宮頚癌の患者数は、40歳代に多いですが、O期、I期の早期癌は、30歳代に多く、III期以上の進行癌の割合は60歳代に多いというデータがあります。また、最近では20歳代に子宮頚癌の増加傾向もあり、若年層に焦点をあわせたスワリーニング検査が大事だと考えられます。
病因と発生
子宮頚癌の発生部位は、子宮頚部の扁平上皮と円柱上皮の接合部である扁平円柱上皮境界(SCJ)とされています。ここに繰り返し刺激が加わり、刺激因子が蓄積すると発癌に到る可能性が高いと考えられます。子宮頚癌が多妊娠や多産婦に多く、また複数の性パートナーをもつ女性に多いことから、子宮頚癌と性交為、STD(性感染症)との関連が昔から注目されてきました。とくに性感染症(STD)の1つであるHPV(ヒトパピローマウイルス)との関係は特に重要と考えられています。しかし、HPV感染自体は、正常女性の約20%に見られるもので、HPV感染だけで癌が発症するわけではないと考えられています。
臨床症状
早期癌では、ほとんど無症状であることが多いですが、浸潤や転移が進むといろいろな症状も引き起こすことがあります。
a)不正性器出血
性交時や性交とは全く関係なく、月経時以外に出血が見られることで、腫瘍の出血容易性が原因です。しかし、癌ではなくても不正性器出血が見られることも多く、あわてず検査を受けてもらうことが大事です。
b)下腹部痛・腰痛・性交時痛
下腹部痛の主な原因は、腫瘍により子宮頚管が狭窄して、子宮膣内に分泌腋が貯留し、ここが細菌感染を起こした事により、膿の排出が妨げられ、発熱を来たし、下腹部を来すケースです。また、このため陣痛様の痛み(Simpton微候)が起こることもあります。腫瘍が広がり、骨盤内神経に及ぶと下腹痛を訴える事もあります。
c)血尿・下血
腫瘍が膀胱や直腸へ浸潤した場合に認められることがあります。
診断
基本的に悪性腫瘍の確定診断は組織学的に行います。(組織診)しかし、その前段階として視診や融診、細胞診等の検査も大事となってきます。
a)視診(膣鏡による)
肉眼的に癌が確認できる場合もあります。この場合、その大きさや広がり、形態についてよく観察することによって診断します。
b)細胞診
子宮膣部のびらん面とその周囲から綿棒等を用いて、擦過した細胞を採取して行う診断法です。(擦過細胞診)一般的に行われている子宮頚癌のスワリーニング検査とは、この細胞診のことです。細胞診の判定法にて、パパニコロウクラス分類という分類法が用いられます。細胞異型の程度によってクラスI〜Vの5段階評価で診断します。
-
class I・・・正常
-
class II・・・異常細胞を認めるが良好
-
class III a・・・悪性を少し疑う。軽度、中等度異形成上皮を想定。またトリコモナス膣炎、組織修復、ろ胞性頚管炎、頚管ポリープなど良性異型の程度の強いものが入ってくる可能性があり。組織学的に調べると、このクラスより5%程度に癌が検出される。
-
class III b・・・悪性をかなり疑う。高度異形成上皮を想定。このクラスよりは約50%程度に癌が検出される。
-
class IV・・・極めて強く疑う。上皮内癌を想定する。
-
class V・・・悪性である。浸潤癌(微小浸潤癌を含む)を想定する。
細胞診にてクラスIIIの以上のケースを要経過観測として癌の可能性があると判断された場合には組織診を行います。
c)組織診
組織診で異常がある場合、癌の可能性があると判断された場合に行います。病変部分を特定し、その部位より組織を採取します。この組織診によって子宮頚癌の確定診断がなされます。
治療法
直行期や転移等によって変わってきますが、上皮内にある場合には、円錐切除等の手術が行われ、浸潤癌の場合には癌の広がりの程度により、単純子宮全摘術から骨盤内臓器全摘術まで様々です。また、放射線療法や化学療法も行われます。
ここでは詳しい説明は省略します。
|